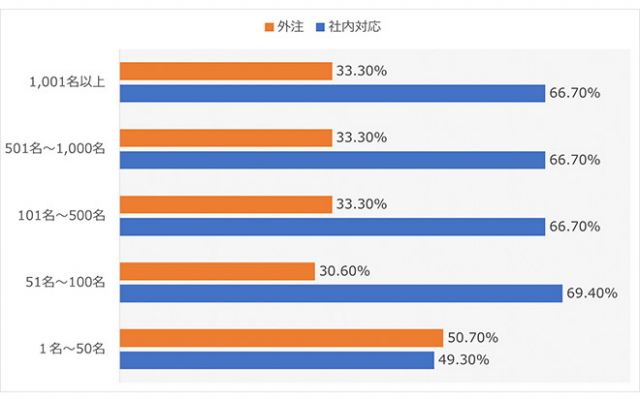BPOを活用し働き方改革を実現するための基礎知識
- 投稿日:2019/1/29
-
カテゴリ:
よくある質問

勤務時間や勤務場所を柔軟に決められる仕組みを取り入れ、個人が生き生きと働く環境を実現するための「働き方改革」。実現に向けて国が率先して音頭を取っていることもあり、ワーク・ライフ・バランスの適正化や残業時間の減少といった具体的な施策を導入する企業も増加しています。
とはいえ、多くの企業にとって働き方改革はメリットもある代わりにデメリットも多く、導入に向けたハードルは決して低いとは言えないのが実情です。労働時間短縮や残業時間の見直し、非正規雇用の待遇改善などコストアップ要因となるような内容も含まれるため、二の足を踏んでいる経営者も多いのではないでしょうか。
そんな中、大都市圏を中心にBPOを導入し働き方改革を実現する手法が今脚光を浴びています。BPO導入と働き方改革を同時に進めることで全体的なコストダウンも可能となるこの方法は、今後多くの企業で検討されていくことでしょう。そこで今回はBPOを活用し働き方改革を実現するための基礎的な知識について解説いたします。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」概要

最初に、平成30年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下、働き方改革関連法)の概要についておさらいしておきましょう。
働き方改革法は、大きく3つの柱から構成されています。
- 働き方改革の総合的かつ継続的な推進
- 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
多様で柔軟な働き方の実現についてはフレックスタイム制の清算期間見直しや高度プロフェッショナル制度の創設などを規定。
- 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
このように、働き方改革関連法の下で一億総活躍社会を実現するための具体的な施策が次々と打ち出されることとなります。
働き方改革関連法により企業側は何をしなければならないのか?

では、この働き方改革関連法の施行により、企業側はどのような変化を求められることになるのでしょうか。そもそも働き方改革には日本における労働力人口の急速な減少という背景があります。2013年には8,000万人いた労働力人口は、今後減少の一途をたどり2051年には5,000万人を切ると言われています。つまり、企業側から見れば労働力確保が今以上に困難となるということです。
労働力を確保するためには働き手を増やすか労働生産性を上げるかしかありません。前述の通り働き手を増やすという選択肢はますます困難となることが明白であるため、企業としては労働生産性を上げるという選択を行う他ないということです。
労働生産性の向上を図るためには、業務プロセスや制度、業務システムの見直しが必須です。つまり、業務の目的の把握や業務内容の洗い出しを行い、そもそもこの業務は必要なのか否か、すべての業務をゼロベースで見直すことが重要となってきます。結果、業務量を減らす、あるいは業務そのものをやめるといったことで、労働生産性の向上を図ることが可能となるのです。
働き方改革を実現するための選択肢のひとつがBPO
とはいえ、自社内で業務の見直しを図ることは本来の業務を止めてしまうことにつながり、逆に非効率となります。また、第三者による客観的な視点を取り入れなければ、既得権化した業務を「やめる」という選択肢に対して社内から不満の声が上がることでしょう。そこで、業務改革のプロフェッショナルであるBPOアウトソーサーの手を借りるというのが最も現実的な選択となります。一部のタスクだけを外部に委託してコスト削減を図るのではなく、社内の構造を変えて業務設計、業務実行、業務管理のすべてを外部に委託するBPOは、企業の労働生産性向上を外部から支える効果的な手法です。BPOにより労働生産性だけでなく業務コストの削減も可能となるケースもあり、BPOが企業の「働き方改革」実現に向けて大きく寄与することは間違いありません。
まとめ:働き方改革はBPOにより実現できること、経営判断の一つとして準備しておこう
このように、働き方改革の実現にはBPOの導入が非常に効果的です。少子高齢化対策やワーク・ライフ・バランスの実現、またテレワークの推進など働き方改革に向けて多くの企業が具体的な取り組みを始めています。これらの施策導入に向けては本来の業務プロセスを見直すことが必須。BPOにより社内業務をゼロベースで見直し、業務プロセスの改善を図ることが今後非常に重要となってくることは間違いないでしょう。